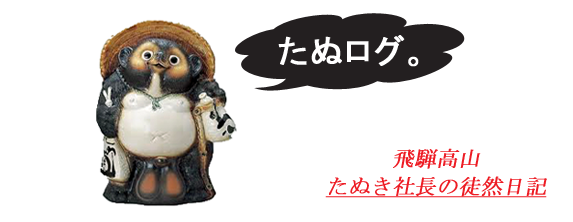スポンサーリンク
「大津祭や大津の歴史を学びましたぁ」・・・!
2019年12月09日
研修会「大津大会二日目」・・・
どこへいっても朝の目覚める時間は一緒で(笑)

5時半には目覚め完了
6時に大浴場
身繕いして、7時レストラン一番乗り


皆さんとお話しながら、ゆっくり朝食をね

タヌは、集合時間まで散歩に・・・

琵琶湖畔のホテルは目の前が「比叡山」でね
午前9時から二日目「研修・視察」が始まりました(^^)

120名ほどを4班に分けて、またそのうち半分でまず曳山「源氏山」の収蔵蔵と
山会所を視察
大津の曳山も祇園祭と同じように祭りのたびに「組み立て~分解」が行われる
のです。ここでは祭りの1週間前に「山建て」と「曳き初め」があります

東海道沿いの「中京町」の「山会所」の細い路地の突き当たりに「源氏山」の部品が
「収蔵」されていました(^^)


組の皆さんの特別なお取り計らいで、「からくり 紫式部」、「車」、「懸装品」はじめ
「構造材」~「天井絵」など展示説明をしていただきました(^^)



また、会所の2階(例祭前は囃子の練習や寄り合いを行う)には、源氏山の「胴幕」
「見送り幕」が出してあり、1600年代に中国で作られた「綴織」の幕(稀少価値)と
それを模して1700年代に織られた日本製のものが展示されました


経年の色褪せの様子からも、中国製のレベルが格段に高いことがわかります
高山にも、当時の貿易品の幕が現存しますが歴史的にも文化芸術的にも価値が
高いものであることが理解できますね
次に、「曳山会館」を見学

「レプリカの曳山」が展示され、からくりも行われました(電動仕様の^^)
大津では、「山建て~分解」が大事な祭礼の行司なので曳山会館にはレプリカの
曳山しかないことが理解できます

学芸員さんの説明では、大津のからくりは東海のからくりとは違うがその原点で
あろうこと、それは高山の屋台の名前と共通項が多いことからもわかるような
殺生石、石橋、蛭子、大黒、布袋、崑崙、鯉、神馬、神攻皇后・・・あるある

山王祭の絵巻(江戸時代)をみても、大津の曳山と形状も似ているなぁと思います
宿場町で道路も狭く、回転の動作の簡略から三輪で製作したというくくりも高山の
三輪の屋台の出現、また戻し車の技術に繋がるところです(^^)
今後の研究や検証に何か夢がひろがりますね


最後の視察は「大津市歴史博物館」
博物館の見学、歴史ある大津のすごさがわかる展示でしたね(^^)
交通の要衝であり、歴史の節目にはこの場所が重要なところ・・・東海道の宿場町
では最大の街、京都大坂奈良など主要地の水がめであり、水運も含めた経済の
要でもある「大津」
博物館の研修室で、最後の座学は「大津のからくり構造と実演」

「西行桜狸山」のからくり(実物)で構造の説明のあと、実演(囃子付き)していただき
間近で質疑応答(^^)
二日目の「研修・視察」も内容も充実したもので、大津の皆さんの力の入れようが
伝わって来ました(^^) すばらしい研修大会となりました(^^)
すばらしい研修大会となりました(^^)
次年度は、4月に滋賀県長浜市で「全国山・鉾・屋台保存連合会総会」、そして
11月に富山県高岡市で「技術者会 研修大会」が開催されます
今回のレベルに対し、プレッシャーだよね(^^)
大津・・・またいきたいところだね


ただね、祭りは「八幡祭」とかさなるんやさな
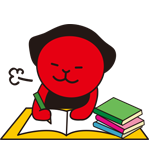

、

どこへいっても朝の目覚める時間は一緒で(笑)


5時半には目覚め完了

6時に大浴場
身繕いして、7時レストラン一番乗り



皆さんとお話しながら、ゆっくり朝食をね


タヌは、集合時間まで散歩に・・・


琵琶湖畔のホテルは目の前が「比叡山」でね

午前9時から二日目「研修・視察」が始まりました(^^)


120名ほどを4班に分けて、またそのうち半分でまず曳山「源氏山」の収蔵蔵と
山会所を視察

大津の曳山も祇園祭と同じように祭りのたびに「組み立て~分解」が行われる
のです。ここでは祭りの1週間前に「山建て」と「曳き初め」があります


東海道沿いの「中京町」の「山会所」の細い路地の突き当たりに「源氏山」の部品が
「収蔵」されていました(^^)


組の皆さんの特別なお取り計らいで、「からくり 紫式部」、「車」、「懸装品」はじめ
「構造材」~「天井絵」など展示説明をしていただきました(^^)




また、会所の2階(例祭前は囃子の練習や寄り合いを行う)には、源氏山の「胴幕」
「見送り幕」が出してあり、1600年代に中国で作られた「綴織」の幕(稀少価値)と
それを模して1700年代に織られた日本製のものが展示されました



経年の色褪せの様子からも、中国製のレベルが格段に高いことがわかります

高山にも、当時の貿易品の幕が現存しますが歴史的にも文化芸術的にも価値が
高いものであることが理解できますね

次に、「曳山会館」を見学


「レプリカの曳山」が展示され、からくりも行われました(電動仕様の^^)

大津では、「山建て~分解」が大事な祭礼の行司なので曳山会館にはレプリカの
曳山しかないことが理解できます


学芸員さんの説明では、大津のからくりは東海のからくりとは違うがその原点で
あろうこと、それは高山の屋台の名前と共通項が多いことからもわかるような

殺生石、石橋、蛭子、大黒、布袋、崑崙、鯉、神馬、神攻皇后・・・あるある


山王祭の絵巻(江戸時代)をみても、大津の曳山と形状も似ているなぁと思います

宿場町で道路も狭く、回転の動作の簡略から三輪で製作したというくくりも高山の
三輪の屋台の出現、また戻し車の技術に繋がるところです(^^)

今後の研究や検証に何か夢がひろがりますね



最後の視察は「大津市歴史博物館」

博物館の見学、歴史ある大津のすごさがわかる展示でしたね(^^)
交通の要衝であり、歴史の節目にはこの場所が重要なところ・・・東海道の宿場町
では最大の街、京都大坂奈良など主要地の水がめであり、水運も含めた経済の
要でもある「大津」

博物館の研修室で、最後の座学は「大津のからくり構造と実演」


「西行桜狸山」のからくり(実物)で構造の説明のあと、実演(囃子付き)していただき
間近で質疑応答(^^)

二日目の「研修・視察」も内容も充実したもので、大津の皆さんの力の入れようが
伝わって来ました(^^)
 すばらしい研修大会となりました(^^)
すばらしい研修大会となりました(^^)
次年度は、4月に滋賀県長浜市で「全国山・鉾・屋台保存連合会総会」、そして
11月に富山県高岡市で「技術者会 研修大会」が開催されます

今回のレベルに対し、プレッシャーだよね(^^)

大津・・・またいきたいところだね



ただね、祭りは「八幡祭」とかさなるんやさな

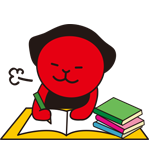

、
Posted by たぬログ at
14:37
│Comments(2)